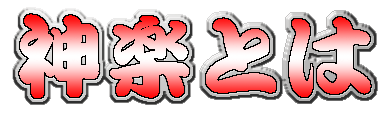
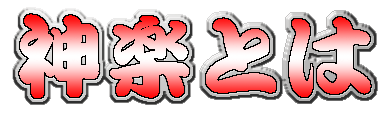
| 神楽の歴史 | 広島県の神楽の歴史 | 新舞・旧舞について |
| 広島県の神楽の歴史 | ||
| 広島の神楽のルーツは島根県八束郡鹿島町の佐陀神社(佐太神社)ではじまった佐陀神能であるといわれています。 佐陀神能とは佐陀神社の神楽師、宮川秀行が神話や諸社の由緒縁起等を題材として猿楽能的に仕組んだもので、中でも重要なものは「七座の舞」と言われ、幣・榊・鈴・茣蓙などを採物とし儀式舞として舞われていました。 そして、これに加えて余興的な意味合いとして、神話などの内容を取り込んだ能である「荒神」、「恵比寿」などが現在でも舞われています。 しばらくして佐陀神能は飯石郡経由で島根県邑智郡に伝わり大きく二つに分かれました。一つは邑智郡石見町矢上を中心として発展した矢上舞で、もう一つは邑智郡羽須美村阿須那を中心として発展した阿須那手です。 矢上舞の楽は六調子でゆったりしたもので、舞もゆったりしています。
|
| 新舞、旧舞について |
| 旧舞、新舞の分類として一般的には『旧舞→矢上系六調子(矢上舞)』、『新舞→高田系八調子(高田舞)』として分類されがちですが実際の分類としては『太平洋戦争前に創られたもの→旧舞』、『太平洋戦争後に創られたもの→新舞』と分類されるそうです。ですから矢上舞の新舞や高田舞の旧舞も実際にはあるそうです。 例えば塵倫は矢上舞では鬼が一匹しか出てきませんが高田舞になると三匹でてきます。ですが、これは昔から鬼は三匹でるものであり、改編などは行われていないので旧舞になります。 その他高田舞での旧舞を挙げるとすると、「八岐大蛇」、「塵倫」、「鐘馗」、「神農」、「八幡」などの儀式舞の各種です。 矢上舞の新舞は基本的にはありませんが、競演大会等で注目を浴びた高田舞の新舞を六調子の矢上舞で舞う団がまれにあるらしいです。 |
| 参考文献:新泉社「古代出雲と神楽」 |